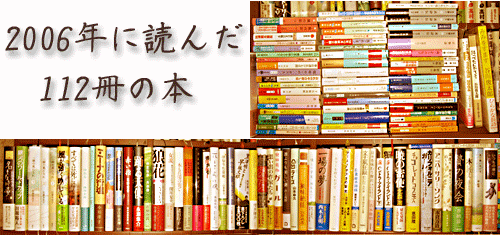|
1月******************************************
山田詠美『風味絶佳』
装丁がしゃれてる・美味しそう。キャラメル風味な小説。肉体労働職人男とその男に居心地の良さを見つけた寂しい女。基地の街でバーを営むスーパー・グランマ!風味絶佳!
山本幸久『凸凹デイズ』
仕事仲間小説。徹夜暴飲暴食。心地よい余韻。ゴミヤのテーマソング「雪が降る町」(byユニコーン)キャラ立ちが良いからテレビドラマにすれば面白そう。
井上荒野『誰よりも美しい妻』
誰よりも美しい妻は夫への愛に絶対の自信がある。夫は浮気を繰り返すけど夫は私から離れられないと判っている。これは寒い寂しい話しなのだと思う。
井上ひさし『宮澤賢治に聞く』
たしかに賢治の作品は宮澤賢治その人を知ってこそ面白さがより判る。あの時代に日本の東北の町に賢治のような人が存在したことが驚きだ。
グレッグ・ルッカ『耽溺者(ジャンキー)』
185cmの女探偵ブリジットのタフなボッディ&ソウルに驚け!(笑)ヒロインがこれほどボコボコにやられる(何度も!)ハードボイルド小説は初めて。ニューヨークのダークサイドを活写。
矢沢あい『下弦の月1-3』
NANAと同じくやたらかっこいいロック・スターが登場。このかっこよさは少女漫画ならでは。ストーリーはミステリー&サイコ・ホラー仕立てで面白い。恩田陸が書きそうなお話し。小説として読んでみたい。
2月*******************************************
岡本行夫・田原総一朗『「外交」とはなにか、「国益」とは何か』
躍進する中国に対する記述が一番刺激的。政治=経済、経済最優先の中国。政府外交の顧問・補佐官という立場の岡本だから、反政府な発言は無し。田原はあくまで現実路線。
あさのあつこ『バッテリーⅣ』
第4話は巧と豪バッテリーの危機編。二人をとりまくチームメイトとライバルと、そんな野球仲間達を爽やかに活写。続編が楽しみ。
瀬尾まいこ『優しい音楽』
ふんわり結びつくカップル。そしてやはり食卓に集う。瀬尾さん得意の優しい食卓小説。そして優しい音楽とは?家族合奏「ティアーズ・イン・ヘブン」。巧い結末。
小池真理子『無伴奏』
仙台を舞台とした恋愛物語。'69年から'70年という学生運動の嵐が吹き荒れていたあの時代を背景としている。主人公は運動にかぶれている自称ゲバルトローザ。反戦フォーク集会、制服廃止闘争など懐かしい。作家小池の青春もなぞっているという。殺人と自殺を含む激しい恋愛模様を描いておきながら、物語は静かで穏やかな雰囲気で語られる。これはその事件の20年後の回想として語られているからか。作者はあとがきで「時代をセンチメンタルに料理し、味わってみようと試みた。」と書き、解説石田衣良は「メランコリック」と書いた。そんな杜の都のセピア色の物語。
小池真理子『恋』
...くすぶったような快感が私を襲う。だが、快感は花開かない。行き止まりの袋小路に追いやられ、それはやがて悲しみに取って代わる。...小池真理子『恋』より。セピア色の悲しい恋物語が終章のマルメロ登場で鮮やかに色づきます。ああそうだったのか!とため息が。
荒山徹『十兵衛両断』
とんでもなく面白い。柳生一族vs朝鮮半島からきた妖術師。奇想天外ぶっとびな伝記小説です。
大崎善生『アジアンタムブルー』
喪失、エロス、'70sロック...。泣けた泣けた。『アジアンタムブルー』にもらい泣き。"
水溜まりの写真 "
に惹かれました。イメージ湧いてくるんだよね。ラスト近く、...「私は幸せだ」。彼女の短すぎる人生で見つけた、それが最後の水溜まりだったのかもしれません。...良い物語でした。文庫本なのに最後の解説文がなく、物語の余韻に浸ることができました。
野沢尚『龍時02-03』
ゲームとプレイの描写が巧い。フィールドに立ってプレイしている感じでその臨場感が凄い。スペイン・サッカー、サッカーをとりまく町と民衆を活写。単身スペイン・サッカーに身を投じた茅野龍時17才のサッカーと恋。
3月感想文*******************************************
奥田英朗『ガール』
30代独身キャリアウーマンを描いて愛しい短編小説集。涙あり笑いあり嫉妬あり諦めあり、でもラストにはきっちりと希望を描く。
ジム・トンプスン『おれの中の殺し屋』
強烈だった。もう読みたくないな。殺人者が一人称で語る小説なので人格が壊れている(壊れていく)様がいっそう恐い。もの凄く周到に作られた巧い小説だからこそ、読者に何とも言えない(イヤな)読後感を押しつける。スティーヴン・キングが熱い賞賛の解説を寄せている。世に恐い物好きって多いよね。
浅田次郎『椿山課長の七日間』
「献杯」佐伯知子の純愛に感動してジ~ンとし、椿山の父さんにまたホロリ。まったく椿山ったら(怒)。よくもこんな奇妙で面白い話しを思いつくものだ。死んだ人の視点からの家族小説なんですね。でも物語は明るく爽やか。つくづく巧いなあ。
上原隆『雨にぬれても』
『雨にぬれても』にはやられたな。彼の作品をどんどん読んでみたい。短編小説集かと読み出したんだけど、一話一話がやたら短い。その短さに、最初は物足りなくノレないなって感じながら、どんどん読み進める。そしたら、ああそうか、面白いんだ、と病み付きになる。どの話しにも結末っぽいものがない。オチがないんだよね。だからそれぞれの小さな物語の登場人物が、読み終えた後になってもそのへんに生きていてナンカ気になるんだな。こうした作品はルポルタージュ・コラムと上原さん自身が命名している。ノンフィクションだったんだ!現代 日本の市井の物語。するどい!
広谷鏡子『花狂い』
もう他人事でない世界かなあ...などと色々考えながら読んでいる。初老小説でしかも情痴小説で...老醜..老臭(笑)。
栗田有起『ハミザベス』
なんかわからんお話しながら読みやすくてあっという間に読めました。あんまりスーっと読めたのでナニカ読み残しがないか心配(笑)。
ドナルド・キーン『思い出の作家たち』
谷崎・川端・三島・安部・司馬という五人の作家について書かれています。三島は公然と太宰治への激しい嫌悪を露わにした人で、「仮面の告白」を例に、太宰は自分が周囲の人達と違うから仮面を被って彼等と同じ人間であるように振る舞い、三島は選んだ仮面に自分を作り替えることができ、そしてその仮面を被ったまま死んだ、とあった。
終章は司馬遼太郎。「...愛国的な熱意によってでなく、日本人であることの、歴史を通じた冷静な認識によって、彼の著作は国民全体を鼓舞したのである。...市井の最も平凡な人々の人生さえもが賞賛に値するものなのだと説いて、日本人を慰撫し、勇気を与えた。」とある。司馬さんは国家主義を嫌悪しました。そして国家を持たぬバスク民族が固有の言語と文化を誇りと共に堅持する様を熱く見つめるのでした。
喜国雅彦『本棚探偵の冒険』
彼がこれ程の古書道楽者だとはね。なんかねマニアな気持ちって分かる気はしてたけど、収集が目的な人達はハタから見たら異人変人て気がしてきた。愛すべきマニアの世界だね。
4月*************************************************
T・ジェファーソン・パーカー『サイレント・ジョー』
不幸な生い立ちとその傷跡を背負い生きてきたジョー・トローナ。ラジオ番組に引っぱり出され「あと2秒残っているから、自分のことを単語ふたつで表現してみて」とせかされ「needs
Improvement(改善の余地あり)」と答えたジョー。さて物語は...。"物静かな"ジョーが主人公なので、物語は穏やかに進行。で内容はまったく不穏。人物描写が丁寧で登場人物が多いのに読んでいて混乱がない。謎解きを進行させつつ、親子小説(とくに父と息子)、恋愛小説としても読ませてしまう。う~ん巧い小説だ。
浦沢直樹『プルートゥ3』
原作の手塚版を換骨奪胎、ここまで面白く膨らませてくれるとは!!!いやはや素晴らしい作家です。あの可愛らしい少年アトムをどの様に戦わせるのか、こっちの想像も膨らんできます。
伊坂幸太郎『ラッシュライフ』
面白いと感じながら読んでるけど、響くものがないんだな。キャラにコリすぎな感じもするし。
西木正明『一場の夢』
昭和を33年生きた者として、ここに書かれている美空ひばりをめぐる話しは興味深く、その昭和の香りを伴う歌謡曲という流行歌に懐かしさを憶える。
原田マハ『カフーを待ちわびて』
カフーとは沖縄与那喜島方言で【果報】良い報せ・幸せ、とあります。沖縄の小島を舞台にしたラヴ・ストーリーでした。宣伝文句に惹かれて(主人公はさえない"
よろづや"が生業で俺みたいだし)読んで みました。沖縄を舞台にするとだいたいこんな人の良い話しになるんだよね。はい良いお話しでした。
佐藤亜紀『天使』
なかなか物語を掴み切れぬままラストまで引きずり回され、ようやく一条の光が(笑)。手強かったけど面白かった。この凛とした媚びない文体は素晴らしいです。
海堂尊『チーム・バチスタの栄光』
面白いとは思うけど、こーゆーのあまり好きじゃないんだよな、と読み進み、犯人が捕まった後のエピローグでストンと俺の心に落ちた。そうか...なるほど...。キャラで読者を振り回しておいてラストでストン。おそれいりました。
畠中恵『しゃばけ』
舞台は江戸、大店の病弱な若旦那と妖(あやかし)達が力を合わせて事件を解決するお話し。設定が面白い、けど若旦那の"助さん格さん"ともいえる犬神と白沢が肝心なときに弱い(笑)。
5月*********************************************
ロバート・マキャモン『少年時代』
楽しかった~!!これぞ読書の醍醐味です。ミステリー、ファンタジー、ホラー、恋愛、成長、悪漢、ガンマン...などなど、あらゆるタイプの物語が詰まっていて、それぞれが味わい深い短編小説でもあるんです。少年の目と心で書かれた物語です。だから好奇心がキラキラと輝いています。
瀬尾まいこ『図書館の神様』
瀬尾さんの小説には、ヒロインの傷ついた心のコリをさりげなく解してくれる優しいサポーター男がいつも登場します。兄弟であったり、たまたま出会った青年であったり。そしてヒロインが新しい第一歩を踏み出すところで物語は終わります。希望を抱かせる結末が好きです。
永井するみ『唇のあとに続くすべてのこと』
昨日は "
希望を抱かせる結末(小説)が好きです "
と書いたけど、希望もゴールも見えない小説もまたスリルがあって良い。恋愛小説というか中年官能小説なんだけどミステリーでもある。引き込まれました。まあ世間的に言えばイケナイ男女の物語なんだけど、古今東西、愛は善悪の範疇とは無縁てことなのかな。
北方謙三『黒龍の柩』上下巻
ラスト、なるほどそうきたか(笑)。土方歳三を主人公としたこの作品、なかなかスリリングで面白かった。薩摩の間諜と戦いながらの慶喜逃避行、中村半次郎との対決とかね。けど俺が北方謙三に期待した方向とは少しずれていました。男しかいない小説、だからかな...。
奥田英朗『マドンナ』
職場に現れたマドンナへの浮気心を読まれまいとヒヤヒヤドキドキ小心者の中年男に親近感(笑)。
小路幸也『東京バンドワゴン』
4世代同居の賑やかさ、しかも女性陣は美人揃いときた。も~テレビドラマ化してくれ~って感じミエミエの小説だなと読み終えた。巻末に「あの頃、たくさんの涙とお笑いをお茶の間に届けてくれたテレビドラマへ。」とあり、なるほど全編オマージュなのか!寺内貫太郎なわけだ。ああ面白かった!。
雫井脩介『クローズド・ノート』
ヒロインの死(の予感が)が物語り中併走しているというのに爽やかな読後感。二人のヒロインから放たれる爽やかさかなと思う。素晴らしい警察ミステリーだった『犯人に告ぐ』と同じ作者なんだよね、びっくり。ヒロインのひとりは小学校4年生担任で、その教師と生徒達の描写が繊細で温かくてとても惹かれた。うちの娘も小4だし、子供達に細やかに接してくれている先生達も身近な存在だからかな。雫井さんの担任教師とその生徒達に対する温かい眼差し、その謎が解けたのは後書きを読んだ時。雫井さんには不慮の事故で亡くなられたお姉さんがいて、小学校の教師をしていた。そのお姉さんの遺品の中に教え子からの手紙や卒業文集そして連絡帳や学級通信などがあり、雫井さんは亡き姉を偲びそれらを読んだ。そしてこの小説冒頭の学級通信「太陽の子通信」には、そのお姉さんの文章が使われているとのこと。この小説は、亡き長姉への想いと共に書かれた、だから温かくちょっと切なくなのに爽やかなのだと感じた。
川上弘美『夜の公園』
リリと親友の春名は共に35歳。リリには夫が居て春名は独身教師。二人には若い恋人がいる。その若い恋人ふたりは兄弟。春名はリリの夫ともホテルに行く仲。今回の川上さんはこんなお話し。乾いているなあ~って感じ。
6月******************************************
西村雄一郎による評伝『黒澤明と早坂文雄~風のように侍は』
感動を越えて早坂文雄の仕事に圧倒された。凄すぎて感想の言葉が見つからない。肺結核を抱えながら猛烈に音楽を創造し続け41歳で逝ってしまった早坂文雄。黒澤明、溝口健二という二大巨匠に愛され、武満徹、芥川也寸志、湯浅譲二といった後輩作曲家から慕われた。伊福部昭とは同い年、札幌で音楽活動を始め研鑽した同志でありライバルだった。~
風のように侍は 大地の上を吹き過ぎる ~
笹生陽子『楽園のつくりかた』
~
ぼくの希望はエリートコースをまっしぐらにつき進むこと。中高一貫教育をへて、一流名門大学へ進み、一部上場企業に就職.....そんな中学生のぼくが、あろうことか山村の中学校しかも分校に転校。同級生3人。ここから物語は始まります。面白かった、けど、もうちょっと続きを読みたかったな。
吉本隆明『日々を味わう贅沢』
大先生の好々爺エッセイ。飄々としかしその観察眼は流石の大先生です。食中毒ならぬ食欲中毒であると大先生は告白する。食べものの欲望にうち克つのが、何よりも難しいというのがその症状だそうだ。それなら俺だって食欲中毒であると胸を張って言える。
大川渉『文士風狂録』
今の日本では絶滅危惧人種である「文士」がたくさん登場。もうそれだけで嬉しい悲鳴(笑)。銀座のバー「ルパン」のカウンターに太宰と安吾と織田作之助が腰掛けて、写真家林忠彦がひっそりカメラで狙ってる...。いいねいいねえ(笑)。
大沢在昌『パンドラ・アイランド上下』
2004年の柴練賞受賞作です。柴練賞と山周賞は数ある文学賞の中で一番信頼しています。この大沢『パンドラ・アイランド』ですが、読んでくうちになんだか金田一耕助モノみたいになってきて面白かった。殺人阻止率が低いとか。絶海の孤島、旧村民vs新村民、村の隠し財産みたいなモノ、顔のない死体ってのもあった。主人公はそんな島に雇われた保安官。横溝調大沢ハードボイルドって感じ。大人のエンタテイメントですね。
7月***********************************************
北森鴻『暁の密使』
日露戦争直前、日本の僧がチベットのラサをめざす。久々の冒険活劇小説に期待大だっただけに、活劇的盛り上げの少なさと結末のつまらなさにガックリ。主人公の影が薄いんだなあ。残念でした、はい。
中村航『リレキショ』
僕(主人公)とウルシバラはリレキショを眺め...嘘みたい。「都会のおとぎ話しなのかな」とつぶやく。おとぎ話しだねえ、と俺。あんな素敵なおネエさんと暮らしていてエッチ心が起きないなんて、まるでおとぎ話しだね((笑)。この頃の若手男性作家は男を描くのがヘタだと思う。
畠中恵『ぬしさまへ』
ご存じ『しゃばけ』シリーズの2作目ですね。着想が面白いよね。今回は仁吉の時空を越えた片思いにやられました。ケン・グリムウッドの『リプレイ』に似たお話しなんですね。
恩田陸『チョコレートコスモス』
そうか、ラストに始まりの予感なんだね。始まりのラストに向けてオーディションが進行するんだ。だからこの物語は終わっていない。素晴らしい余韻です。
T.J.パーカー『カリフォルニアガール』
'60年代後半のカリフォルニアを主な舞台にしていて、ニクソン、ティモシー・リアリー、チャールズ・マンソンなど対立するアメリカを映し出す人達も登場。警察小説であり家族小説でもあり、なんだけど、回想として書かれている感じが付きまとい、押さえた筆致のせいかスリルに欠けるかな。際立った(魅力的な)登場人物がいないので引き込まれ度が低かったね。
垣根涼介『ワイルド・ソウル』上下
極上の活劇エンタテイメントでありながら日系ブラジル移民哀史でもある。上下巻まったくダレることなくキャラ立ちも見事。参りました。
8月************************************************
香納諒一『贄の夜会』
ふぅ~っ、ようやく終わった。極上のサスペンスだったな。警察小説、スナイパー小説、サイコ・キラー小説(クラリスとハンニバル・
レクターのような!)、これらすべてをぶち込んだ作者渾身のスリル&サスペンス小説の傑作ですよ。
あさのあつこ『バッテリーⅤ』
中学生って危うい年代らしいね。これ読んでると作者は野球に名を借りて少年達の心の成長を書きたいのかなって気がする。仲間達がいてライバル達がいて家族がいて、そして野球があって、そのブレンド具合が心地良い小説です。もう5巻まできましたね。少年達の成長をどこまで見つめることができるのでしょうか。
藤原緋沙子『夢の浮き橋~橋廻り同心・平七郎控』
木槌を十手代わりってのが面白いね。程良い年増の姐さん達(笑)も素敵だし。捕物帖としても人情話としても良い感じの物語でした。
森浩一『日本神話の考古学』
巻末エッセイ中山千夏ってのにたまげた。革新自由連合だっけ?もっと頑張って続けて欲しかったな。
横山秀夫『クライマーズ・ハイ』
小説の最終章にたまにある後日談てのが好きだな。物語が壮絶であればあるほど一件落着後のあの人達は...みたいなお話し。クールダウンできるしね。男達の自我と欲望が激しくぶつかり合う新聞社内。それと対比する谷川岳衝立岩の静謐さ。日航ジャンボ機墜落事故とその17年後。小説の縦糸と横糸を巧に織り上げる作家の力量。読みながらいろんな事を考えさせられました。素晴らしい小説です。
今邑彩『いつもの朝に』
殺人事件に関わる出生の秘密を抱えて岡山県の山奥の村へ、そこの粗末な家には一人暮らしの老婆が少年を待ち続けていた...。なにやら金田一耕助風(笑)。ところが、物語の空気は澄んでいて以外や暗くない。これは主人公が中学生の兄弟であり、会話に中学生らしさが横溢しているからだと思う。兄弟がモンダイを最後まで母親にうち明けないとこなんて、いちおう俺も父親なのでハガユかったな。
瀬尾まいこ『強運の持ち主』
たまたま占った男がもの凄い強運の持ち主とわかり、強引に自分の彼氏にしてしまった占い師ルイーズ吉田。このルイーズと彼氏通彦さんを中心としたホンワカ小説。瀬尾さん好きだから、まあこれもいいんじゃないかな(笑)。
永倉万治『アニバーサリー・ソング』
残念ながら早死にしちゃったけど、うらやましい人生って気もするね。俺よりひとまわり年上の東京人。面白い話しで回りの人達の気を逸らさない人気者だったのかな?エッセイのような私小説のような短編集。面白くそして唸らせもする、いい本です。
上原隆『喜びは悲しみのあとに』
著者名付けるところのルポルタージュ・コラム。タイトルはキャロル・キングの曲から。この本は『友がみな我よりえらく見える日は』の続編で、内容はまさにこれです。落ち込んで凹んで、そんな状態からのリスタートがテーマ。読んでいるとちょっと元気が出ます。解説の中で鶴見俊輔は
"
全体主義とは無縁と思われた米国が全体主義に近づき、一度は全体主義から抜け出したと思われた日本がふたたび全体主義に入り込む この時代に、あきらかにこの現代日本の中から、時代を超えて、読者に呼びかける反全体主義の作品である。"
と書いている。当たってるなあ、全体主義化。若者達を見てると"
明るい全体主義 "
だもんね。全体主義ってのは無意識に少数意見を封殺するんだよね。恐いねえまったく。俺なんか天の邪鬼でマイナー指向(古いね)だからね。あ~あ、なんか息苦しくなってきた。
角田光代『エコノミカル・パレス』
そうか、角田光代はこうゆう小説を書いていた時期があったんだ。初めて読んだ彼女の作品が『対岸の彼女』だったからちょっとびっくり。コンビニで買った商品名と値段を事細かく羅列する箇所が幾度か登場し、その急かせるようなリズムが物語を貫いているように感じました。どこかヤサグレ風情のフリーター小説。
塩野米松『木の教え』
先ず宮大工の口伝の章。木を買わず山を買え、木は生育のままに使え、日表・日裏、木を組むには癖で組め、寸法で組まずに癖で組め...など厳しいながら面白くためになります。これだけ木の恩恵に囲まれた生活をしているのに、木のことを知らない私です。文中で『日本書紀』にふれていて奈良時代に作られた『日 本書紀』の中のスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した後の話し。~
スサノオはこの国には船がないからとそれを造るために体の毛を抜いてまいたとさ。「顔の髭をまくと杉、胸毛をまくと檜、尻の毛は槇、眉毛は樟になりました」とさ。そして「杉と樟は、この二つの木は浮宝(船)とせよ。檜は瑞宮(立派な建物)をつくる材料とせよ。槇は棺をつくる材料にしなさい。また食料としての木の実をたくさんまき、植えなさい。」と『日本書紀』にあるんだとさ。なんと!木の使い方を教えているわけですね。『日本書紀』に対する見方がちょっと変わりました。
9月***********************************************
森絵都『風に舞いあがるビニールシート』
短編集だったんですね。今年度上期直木賞受賞作。『いつかパラソルの下で』の時に受賞して欲しかったな。より森さんらしい作品だと思うから。『風に...』であれっと思ったのは「鐘の音」と「ジェネレーションX」の2編。これは男の世界なんですね。女性を生き生きと描いてきた森さんの印象があったので以外でした。でもどの短編も巧いです。でも俺は『いつか...』の方が好きだけどね。
高村薫『照柿』
『マークスの山
上下』と同じく文庫化にあたり全面改稿とあり興味をそそられました。高村薫は『リヴィエラを撃て』で圧倒されて依頼『レディ・ジョーカー』までは全部読んでるはずです。好きな作家です。で、この全面改稿された『照柿』だけど、ディテールがより細かくなっているような...。だからなのかリズムに乗れません。ああ疲れた。暗い情念の炎にジリジリ炙られ続けヘトヘト。描写が精密で台詞が少なくて...読書修行ができました(笑)。
川上弘美による恋愛小説アンソロジー『感じて。息づかいを。』
ディープな恋愛小説集でした。恋愛という人間関係に深く切り込んだ川上さんの編集感覚って凄いね。坂口安吾「桜の森の満開の下」、車谷長吉「武蔵丸」、野坂昭如「花のお遍路」、よしもとばなな「とかげ」、伊藤比呂美「山桑」、H・エリスン「少年と犬」、川上弘美「可哀想」、藤枝静男「悲しいだけ」の8篇、それぞれに異なるタイプながら味わい深い短編ばかり。ああ満腹です。
北原亞以子『歳三からの伝言』
土方歳三モノです。つまり最後は判っているのです。史実として曲げられない事柄も多いはず。史実を追うばかりのつまらない時代小説もあります。でもこの小説では歳三は勿論のこと松本良順、伊庭八郎そして美乃の存在が物語をふくよかにしていて好感が持てました。
角田光代『夜をゆく飛行機』
不思議な温かさを持った物語でした。世間的には不幸の連続で、登場人物も皆悩みを抱えていて、でもいつもどこかに温もりを感じさせる物語。この4人姉妹の両親は「ちびまる子ちゃん」の両親に似てる。そしてこの父役は三宅祐二がいいな(笑)そんな感じなんだよ。角田さんの新しい一面を見せてもらいました。とても良かった。
10月***********************************************
マイクル・コリータ『さよならを告げた夜』
主人公はクリーヴランドの私立探偵。相棒がいてパートナーの女性がいて、大富豪がいてマフィアのボスがいて、そして魅惑的な女性がいて。いかにもハメット、チャンドラーの後継者である。まだ20代の若い後継者。だからか、どこか爽やか。ワイズ・クラックが少なく進行がスピーディー。とても面白かった。探偵リンカーン・ペリーの物語、第二作も早く読みたい。
万城目学『鴨川ホルモー』
なんじゃこりゃ~な怪作...なのか~?は、でした、怪作(笑)。でも真っ当な青春小説だったりします。これ読んでると、ああ俺も京都で学生時代を送りたかったという想いに駆られました。青春は二度と来ない。う~残念!
荻原浩『僕たちの戦争』
巧いな~読ませるな~のパラレル・ワールド物。ラストが非常にもったいぶってる。オチがはっきりしないんだもんね。こっちが勝手に想像するしかない結末。まあこれもいいかな。
諸田玲子『木もれ陽の街で』
『あくじゃれ』の諸田さん、本作の舞台は戦後27年頃の東京西荻。良家のウブなお嬢様の恋愛話し。与謝野 晶子の歌を巧に用い、古風で上品な趣のある物語。現代でもなく時代劇でもなく、ちょっと昔の東京と日本人を描いた物語に好感がもてました。
三浦しをん『まほろ駅前多田便利軒』
面白かった。TVドラマ向きな小説だね。主役脇役ともにキャラ立ちいいから。主役コンビにイケメン使えるからほんとドラマになるかも。行天役はオダギリジョーがいいな。
川端裕人『銀河のワールドカップ』
日本の小学校6年生少年少女8人が、なんとレアル・マドリッドの主力8人とミニ・サッカーで戦うという物語。ありえない設定なのにウソ臭さを感じさせない面白さ!サッカーへの愛が伝わってきました。嬉しかった!
西原理恵子『いけちゃんとぼく』
西原理恵子初めての絵本らしい。笑わせて、油断させといて、そして愛しい気持ちがストンと心の底に落ちてくる。♪単純に
簡単に 唐突に あっけなく~愛を感じるかもしれない~♪
ってふちがみとふなとさんの「お店やさん」みたいだね。
浅田次郎『地下鉄(メトロ)に乗って』
映画見る前に読んでしまえ、と駆け込み読書(笑)。父と息子の葛藤劇なんですね。その仕掛けに地下鉄そしてタイムスリップ。俺も若い頃は考えたことなかったけど、この頃父親にどんな青春があったのか、どんなヤツだったのか、きっと俺の知らない青年の顔があったはず、とか想いをはせる事がある。知らないのに懐かしいのは何故なんだろと思ったり。それはともかくこの物語、みち子が可哀想すぎるよ。
宮部みゆき『名もなき毒』
読み始めてあれっこの人達..以前会ったことがあるぞ?そうか『誰か』の続編なんだなこれは。探偵みたいなことをしているだけのサラリーマン杉山三郎。冴えてるのか冴えてないのか判らないこの三郎氏あっての物語。むかついて殴りたくなる毒女原田いずみのような悪役は宮部さんの得意とするところ。俺的には『ぼんくら』『日暮らし』の続編が読みたいところです。
三浦しをん『風が強く吹いている』
物語の中の一年間にこっちもきちんと付き添った感じで、読み終わりには、一年前は...とか回想したり(笑)。シロウト同然の大学生達が箱根駅伝に挑むという、ありえないのかもしれないお話し。メンバー10人、ひとりひとりの思いを綴ることで、爽やかな青春小説となっておりました。
佐藤多佳子『一瞬の風になれ
1.イチニツイテ』
大学生の箱根駅伝に続いて今度は高校陸上部の物語。佐藤さんは作品毎に趣向を変えて楽しませてくれる大好きな作家です。続編を早く読みたいねえ。
永瀬隼介『踊る天使』
業火を背負った二人の男をめぐる新宿歌舞伎町ミステリー。あの歌舞伎町雑居ビル火災を物語に取り込み、火災現場のリアルな描写は読んでいるこっちが熱苦しくなる程。手紙文による回想で事件の背景を語り、その構成の巧さに唸った。ちなみにこれを読むとサン=テグジュペリの『夜間飛行』を読みたくなります。えっ!?(笑)
東野圭吾『赤い指』
ヒューマン・ドラマだなあ。深層心理まで潜りこんでミステリーを組み立てる巧さ鮮やかさは相変わらず。チリンという鈴の鳴る音に東野圭吾を感じます。
大沢在昌『狼花-新宿鮫Ⅸ』
この大沢には疲れました~。説明が多すぎて最後まで物語りに乗れなかった。魅力在る登場人物を配置しながら魅力満開まで行けないのは、いちいち長い説明が入るからと思う。苦悩する鮫島。国家・組織・権力に対し個人はいかに対峙できるのか。大きく重く深いテーマに挑んだのだろうか?苦悩する大沢在昌...なのか?。
宇江佐真理『聞き屋与平-江戸夜咄草』
現代ミステリ3連ちゃんで胃もたれ(笑)なのでサラっとした読み物。『聞き屋与平』は良い味出てました。与平のかみさんと3人の息子の嫁さんが揃ってキリっとして魅力的。続編はおかみさん主役で『聞き屋おせき』でお願いします。与平の老いていく日常がせつない小説でもありました。
吉田修一『初恋温泉』
胃もたれなしの短編集。もすこし食べたいってとこでお膳を片付けられた、けど美味しかった、てな感じでしたね。
11月************************************************
佐藤多佳子『一瞬の風になれ
2.ヨウイ』
『一瞬の風になれ
3.ドン』
「人生は、世界は、リレーそのものだな。バトンを渡して、人とつながっていける。一人だけではできない。だけど、自分が走るその時は、まったく一人きりだ。誰も助けてくれない。助けられない。誰も替わってくれない。替われない。この孤独を俺はもっと見つめないといけない。俺は、俺をもっと見つめないといけない。そこは、言葉のない世界なんだ...たぶん。」(佐藤多佳子『一瞬の風になれ
3.ドン』より)爽やかな高揚感。読んでいる間ず~っと良い気分。高校生スプリンターの、そして400mリレーの情景が鮮やか。よくぞ書いてくれた。
森絵都『DIVE!!』上下
文庫本解説は上巻あさのあつこ、下巻佐藤多佳子だ。素晴らしきトライアングル!。佐藤多佳子は書いている。「私は好きな本が終わってしまったことが悲しくて、自分勝手に"続編"を書いたりしていた。...好きな本の世界の中には、いつまでも、いつまでもいたいものだ。」と。俺だって『DIVE!!』のこの後の書かれていない物語とずっと付き添って行きたいと思ったよ。登場人物がみんな生き生きとしていて、いろんな苦難葛藤もあるんだけど、ほのぼのと幸せに笑える物語だから。そしてこれが今年の99冊目なんだよね。100冊目はどれにしようかな。本を読む幸せ(笑)。
シンシア・カドハタ『草花とよばれた少女』
主人公スミコはカリフォルニアの花農家で育った少女。日米開戦、アメリカ日系人の強制収容と収容所の様子がスミコの視線をとおして語られています。先の見えない希望の持てないような状況の中、それでもどこか温かくユーモアを忘れない、そんな人々に囲まれた日々を澄んだ眼差しで描いています。原題は「weedflower」野に咲く花です。今年の100冊目に読もうと取って置いた本です。とっても良かった。
カルロス・ルイス・サフォン『風の影』上下
満腹です。読書の醍醐味を味わいました。作者サフォンはバルセロナ生まれ、物語の舞台もバルセロナ。バルセロナと言えば今ならサッカーのロナウジーニョのいるFCバルセロナだけど、この街はスペイン内戦の傷跡が人々の心に深く残る街でもあります。オーウェルの『カタロニア讃歌』を読んだ人なら、この正義や大義が一晩で逆転してしまうような精神的にも耐え難い内戦が、カタロニアの人々に根深く影を落としていることを知ってしまったはずです。『風の影』はこの内戦の前・中・後のそれぞれの時代を背景に、10才の少年が「忘れられた本の墓場」で手に取った1冊の物語と幻の作家の謎を追うミステリーであり、そこに恋愛、友情、悪漢、風俗など様々な物語が巧妙に織り込まれていて、読む者をぐいぐいと物語の迷宮に引き込んで行きます。ああ面白かった!しばし脱力(笑)。
北方謙三『水滸伝1』
待ちに待った北方水滸伝の文庫化。宋江、晁蓋、魯智深、林冲、盧俊義、史進など、懐かしい顔ぶれ。と言っても以前読んだのは横山水滸伝なんだけどね(笑)。
沢木耕太郎『無名』
沢木が尊敬し愛しそして畏れた自分の父親を書いた。その最期を看取り、そして父の人生に想いをはせる。俺はどうだろうかと思う。生まれてからずっと一緒に暮らし一緒に仕事をしている両親について、なにか特別な思いを持つのは難しい気がしている。いまは二人とも元気だからなのかもしれないが。
小川洋子『ミーナの行進』
"
ちっちゃくて、目と髪が栗色で、芦屋で本当に一番利発な少女ミーナ
"(小六)とわたし朋子(中一)とポチ子(偶蹄目カバ科コビトカバ属)、そしてミーナの家族の物語。カバをこんなに愛おしく感じたのは初めてで、おしまいにはちょっと涙が...。小さなマッチ箱の絵から生まれる壮大な空想の物語がとても良かった。挿画(装幀も寺田順三)も物語にピッタリで、カバーを外すとカバカバカバ...だし(笑)、とても素敵な1冊でした。
12月************************************************
関川夏央『女流~林芙美子と有吉佐和子』
はやしふみことありよしさわこは一発変換だね。関川はこの二人について、才能があって過剰なまでに個性的、生命力に溢れすぎた...後進ギアを持たず、エンジン冷却装置に構造上に難点があった..人間関係の円滑さより自分の仕事の方をはるかに重く見る...と書いた。この本を読む限り、この二人を凄い人達と思いはするけど、近くには寄りたくないとも思う。有吉佐和子はあの
" まるまる有吉佐和子 "
だった「笑っていいとも」に出演した数ヶ月後に亡くなったんだよね。それはよく憶えている。
西川美和『ゆれる』
映画を見た後で読もうと思ってたんだけど、ちょっと読み始めてみたらぐいぐい引き込まれた。それでも我慢して半分で止めといて、そして映画を見た後で最後まで読んだ。登場人物がそれぞれ一人称で語る構成は芥川龍之介の『藪の中』に似ているなと思っていたら、作中に「藪の中」というのが出現!もしやこの構成はソレを意識してのことかな。映画のノベライズ本かなと軽く考えていたら、いやいや小説としてじつに立派。西川さん、小説家としもお見事です。芥川賞、直木賞も夢じゃない!
杉浦日向子『一日江戸人』
杉浦さんによる江戸風俗紹介本です。TV「お江戸でござる」の中で、もう江戸人について語るのが嬉しくてたまらないって感じで喋る杉浦さんが好きでした。日本酒と蕎麦が大好きだったんだよね。彼女は漫画家として青林堂『ガロ』誌上でデビューした人だから馴染み深かった。『合葬』『ゑひもせす』『百日紅』などの漫画で俺は「江戸」の風俗に興味を持つようになった気がしている。もっともっと長生きをして楽しい江戸咄を聞かせて欲しかった(俺よりも2歳下)。合掌。
恋愛小説アンソロジー『LOVERS』
9人の女性作家による短編集。やはり川上弘美、唯川恵、江國香織、島村洋子の作品がアタマ1つ良かった。
ローレンス・ブロック『すべては死にゆく』
待望マット・スカダーの新作です。期待どおりに面白かった。が、凄惨な場面はこの頃イヤになったな。読むのがツライ。それにしてもスカダーさん、68歳ですか!俺が20代の頃に出会った探偵さん達、スペンサーとかね、彼等もいまでは老人の域に達してるんですね。作家もしっかり彼等に年を重ねさせていて、本作ではスカダーが過去の事件や人々を回想するシーンが多くなったのが気になりました。シリーズの終幕が予感され残念なんだけど、スカダーもエレインも満身創痍、もう楽させてあげたいって気にもなりましたね。
北方謙三『水滸伝2』
第二巻は武松から始まりました。武松と潘金蓮の話しって『金瓶梅』なんだそうですね。物語とはそうやって伝承拡散されるわけか。第二巻ではついに晁蓋、林冲達が梁山泊に「替天行道」の旗を立てました、そして吸毛剣青面獣楊志も登場。まだまだこれからですよ。楽しみ。
北方謙三『水滸伝3』
これで今年読んだ本は112冊。初めて目標の100冊を突破しました。読み始めると面白いからどんどん読んじゃうけど、やはり眼が慢性的に疲労しています。もっと頑丈な目玉が欲しかったな。
▲
|