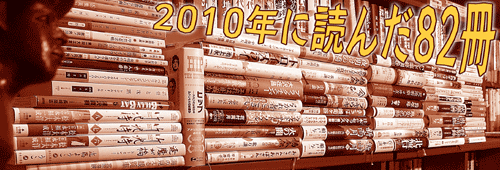|
1月***********************************
川上弘美『これでよろしくて?』
オビを見ずに本編を読み終わり、オビにある "
ガールズトーク小説 "
が腑に落ちる。しかも『婦人公論』連載小説ってことで、どうも男の俺には分が悪い(笑)。川上弘美のニンマリした顔が目に浮かぶ。なんだかなあ...の「これでよろしくて?同好会」、日々の「?」なことをまな板に載せ語り合う会なんだけど、例えば
" パンツ問題 "
ってのがあって、「あの、わたしなら、パンツは脱がされたにしても自分で脱いだにしても、隙を見て自分側の枕の下にこっそり隠しておきます」「枕の下はいいけど、そこに隠していることがばれちゃったら、あたしなら恥ずかしいです、きっと」...とこんな会話が続くわけ。で読んでる俺は、こそこそと隠れ場所を探しつつ耳をパラボナアンテナにしてる(笑)。嫁と姑の静かなバトルがなかなか怖くて、男の俺は避難口へそっと....。
船戸与一『群狼の舞 満州国演義3』
第三巻は昭和7年から。「国家の創出は男の最高の浪漫なんだから」、満州国建国で日本中が沸騰。軍部の独走に懐疑的で反発すら憶えていた奉天領事館の参事官敷島太郎ですら建国の興奮に酔う。しかし...「熱河の阿片は満人に売るんでしょう?満人に売って満人のこころを骨抜きにするんでしょう?」「五族協和だの王道楽土だのはもともと方便に過ぎんのだよ」...と満州国の闇の部分も露呈してくる。満州国の経済を支えたのは阿片の売買だったし、蒋介石の軍費も阿片によって支えられていた。戦争っていったいなんだろうね。
船戸与一『炎の回廊 満州国演義4』
「自由というものはある意味じゃ厄介なものだ。....持て余して捨てたくなったら...自由よりずっと心地いい境地を用意します」「何なんだね、それは?」「国家への隷属ですよ。孤独でしょう、自由は?国家に隷属しさえすればすべてが赦されるんです、どんな残酷な犯罪も。一度、天皇陛下万歳と叫んでごらんなさい。あらゆることが一瞬にして救済されます」と、昭和9年満州で。そして昭和11年の日本は2.26事件により軍事国家が加速。第4巻は建国に湧く満州国から日中戦争(支那事変)前夜まで。船戸にしては人間ドラマが薄い気がするけど、う〜ん...。
浅川マキのエッセイ集『こんな風に過ぎて行くのなら』
読み返していたら、昨日の日記で「時代に合わせて呼吸をするつもりはない」をマキさんの言葉のように引用してしまったけど、この言葉は原田芳雄が言ったとしてこの本に登場していた。しかしかっこいいな「時代に合わせて呼吸をするつもりはない」だってさ。
船戸与一『灰塵の暦 満州国演義5』
日中戦争も北支、上海そして南京へと拡大。その凄惨さにページをめくるのが苦痛だった。戦争というのは人が人でなくなる場なのだ。
さいとうたかお『ゴルゴ13』
ずっと読んでいた船戸与一だけど、彼が小説家としてデビューする前に『ゴルゴ13』の原作を書いていたってのは、ファンならよく知る話し。それでって訳じゃないけど、近く本屋さんで『ゴルゴ
13』の単行本があったので買って読んいた。2005〜2006年の作品が収録されていたけど、久しぶりのゴルゴがまったく変わっていなくて嬉しかった。ゴルゴが歳をとって能力に翳りが見えたり、人生をふり返り物思いに耽ったりしてるのは見たくないなと思った。息の長いシリーズ物小説だったら、その登場人物達の成長や豊かな老いなどを歳月の流れと共に楽しめたりするけど、ゴルゴ13のようなスーパーマンは変わっちゃだめだよ(笑)
伊坂幸太郎『フィッシュストーリー』
初期中短篇が4篇収録。動物園から消えたシンリンオオカミとその檻の前のベンチに夜寝る元飼育員を巡る話。山奥の村に今も伝わる人身御供の話し。売れないロック・バンドと正義の味方を巡るクロニクルっぽい話し。気の良い空き巣達の思わぬ人情話。なんかどれもちょっとヘンだけど着地点が巧いお話しで、伊坂の仕掛けの巧さを楽しめる作品集。なれどやはり初期なんだよね出来映えが。
2月********************************
高田郁『八朔の雪 みをつくし料理帖』
ああ〜美味かったよぅ。ほっこり酒粕汁を食べたみたいに心身がほっこり温まりまったよぅ。舞台は江戸、主人公は裏長屋で以前の奉公先の女将さんと暮らす娘澪。澪は料理の才能に恵まれている。蕎麦屋「つる屋」に奉公しているが、そこの旦那さんが腰を悪くして蕎麦を打つことができなくなり、そこで澪が店を任されることになる。さあて、大阪の味で育ち修行してきた澪に江戸町人を喜ばす料理がはたして...。市井の人情ドラマに料理を絡ませ、ひとりの女料理人が成長していく物語。吉原の花魁からの使い又次は遠藤憲一がいいな、とキャストも考えて(笑)。
矢作俊彦『あ・じゃ・ぱん!』
「誰なんですか?」「東日本の反政府ゲリラ、独立農民党の党首よ。新潟の山奥でもう四十年も戦い続けてるんですって。伝説の人物...」この人物が誰あろう田中角栄!。矢作俊彦『あ・じゃ・ぱん!』の中のお話し。つまり第二次大戦で日本が分断国家になったその後の物語なんだけど....、矢作作品なのにどうもスラスラ読めない。面白いんだけど、この設定のためにいちいち前置きや説明が入ってきて長いんだよね。そのせいでリズミカルに読み進めない。まいったなあ、まだ上巻なんだよぅ。「あなたみたいな失礼な人が、なぜ、そんなに上手なの?」「失礼でないと始められない。上手でないと終わる資格がない」「それって何のこと?」「もちろん人生のことさ」....思わず笑ってしまった。これが矢作俊彦だよね(笑)。『あ・じゃ・ぱん!』上巻をようやく読み終えた。説明調が多すぎて物語が冗長。下巻は後回しだ。
ロバート・B・パーカー『プロフェッショナル』
久しぶりにスペンサー・シリーズを読もうと買って置いたままにしといたら1月にパーカーの訃報が届いた。なんてこった。約十年の不義理を詫び追悼の気持ちを込めながら読んだ。スペンサーはすこし老けていた、でもスーザンとホークとの3人の関係は相変わらず良好で嬉しかった。しかもスペンサーとスーザン、けっこうなお歳のはずなのに、ベッドの上ではいたってお盛んで...いちゃつきっぱなし(笑)。ワイズクラックも健在しこまめに料理もするし、クールなふりしてお節介だし、しょっちゅうビール飲んでるし...ああなんか懐かしくて居心地がよかったよ。
金城一紀『フライ, ダディ,
フライ』
「...『高いところへは他人によって運ばれてはならない。ひとの背中や頭に乗ってはならない』」「....ヨーダ?」「ニーチェだよ」「.....」。一人娘を傷つけられた父親が身体を鍛え復讐に向かう物語。何も知らないで映画を見ていたら、これ漫画が原作でしょ?と思ってしまうようなストーリーだけど、でも断然面白い。エンターテイメントに徹してるところが小説として良かった。
北重人『白疾風』
江戸草創期の武蔵野を舞台とした忍者モノであり活劇であり、そのうえ人物の造形や描写が丁寧で巧い。感心したのでもっと北重人を読むことにした。
3月***************************
北重人『蒼火』
追い詰めているつもりが追い詰められた!しかもそいつは悪鬼のようなやつ!凄かった、面白かった。登場人物それぞれの造形が巧いし情景描写が巧いし...ほんと巧い作家だと思う。『白疾風』でも感じたけど、江戸の町そして近郊の町や村そして街道の様子など、その描写が実に巧みでリアルだ。そうした様子が説明調にならず物語に溶け込みさらに人物達を引き立てドラマに緩急を与えている風なのだ。北重人は全部読もう。
文藝別冊『追悼加藤和彦』
読みながら考えた。もし吉田拓郎の「結婚しようよ」が加藤和彦によるヒットだったら、その後の日本フォークはあんなにも低レベルに歌謡フォーク化せずにきたのではないかと。加藤和彦なら「結婚しようよ」の軽さがシャレっ気で素通りしたんじゃないかと思うんだけど。ついでに思ったのが...、もしアリスが殿さまキングスのような衣装でデビューしていたら、フォークだロックだと間違われずに演歌グループとして今日に至ったのに、...てなことをね。
藤堂志津子『きままな娘わがままな母』
37歳の娘と62歳の母の二人暮らし。娘「欲ばりね、おかあさんは。娘の私をずっと手もとに置くのに成功したら、こんどは孫をうめだなんて...しかも未婚の母のすすめだなんて...」。母「あら、あなたたちが知らないだけよ。私ぐらいのトシで娘を持つ親の究極の本心はそれなのよ。自活できるだけの仕事を持つ娘が、子供をうんでくれて、その子供の父親とは別れて親もとにもどってきてくれること。...」。いやあまいった。男は種馬か(笑)。しかし俺も一人娘の父だから、その意見にはおおいに肯けるなあ。なさけない気もするけど。
北方謙三『楊令伝
十二』
北に金、江南には南宋が興り、中原に金の傀儡斉が興る。斉の国内には梁山泊の国と軍閥岳飛・張俊の支配地域がある。西には梁山泊の交易路となる西夏そして耶律大石の国が興りつつある。これが第十二巻の舞台。そんな広大な舞台や合戦のスペクタクルに負けず劣らず、男達のドラマには静かな感動があった。老兵は志を胸に抱きしめ消えゆくのだった。じい〜ん
川西蘭『あねチャリ』
不登校で引き籠もりの女子高生が自転車競技に目覚め根性だして一花咲かせるっていう、まあシンプルでテレビドラマ的といえるかもしれない。シンプルだけど素敵なお話しとなっているのは、ヒロイン本人の楽天的な性格と脇役達の味わいのよさですね。ひたすら自転車のペダルをこぐ(回す!)というシンプルさから立ちのぼる喜びが、読むこちら側に伝わってきて読後感爽快です。
本間健彦『高田渡と父・豊の「生活の柄」』
しみじみといい本だった。どん底ともいえる困窮生活を送った父・豊と4人の息子達。この本が赤貧の生活を描いても囲炉裏のような温かさが感じられるのは、貧しさに引きづり込んだ張本人の父を息子達がずっと愛し続けた、その温かさだ。結局末っ子の渡は父に似た生き方を選んだわけだし。世間的に一般的に言えばこの父・豊は失格者と呼ばれるだろう、だけど「世間的」とか「一般的」を基準としない生き方を選ぶ者もいる。そんな父・豊が暮らせた時代の寛容さも大事だ。今の非寛容な日本ならより辛い現実が高田一家を襲ったのではないかとも思えた。ほんとうに強くて優しくなければ豊や渡のような生き方はできないよ、と言われた気がした。
佐々木譲『北帰行』
『エトロフ発緊急電』など初期の冒険活劇小説はもちろん、明治維新を幕府・奥羽越列藩同盟側の視線で描き勝海舟をダメ人間として痛快にコケにした『武揚伝』など、佐々木譲は大好きな作家だった。なのに彼が一般的にブレークした北海道警シリーズには食指が動かなかったのは何故だったのか。それがこの『北帰行』を読んで判った気がした。もちろん本書は面白かった。警察小説も犯罪小説も好きだ。だけど、同じように追う者と追われる者がスリリングの交錯する小説でも、『エトロフ...』と『北帰行』では人間味に違いが出る。小説の背景の差だとも思うが。今の日本人はどうしても薄味になってしまうということだ。
久世光彦『触れもせで 向田邦子との二十年』
「...『星影の小径』をいやに長いことハミングしていたのは、何かわけがあったのだろう。きっとその何かが、生きていることのいちばん大切な部分と、意外な関わり方をしているのだ。」感心させられる描写と観察眼にただただ唸る。久世光彦と向田邦子。プロデューサーと脚本家として『寺内貫太郎』を始め多くのヒット・ドラマを生み出したプロ中の一流プロ。そんなふたりのおつきあいを眺める贅沢。田舎では絶対にお目にかかることのないオトナ達に憧れる青二才の俺がいる。田舎のひとは一生懸命田舎自慢をするけれど、俺は都会で生まれ暮らしたかったのだ。
宮本昌孝の『風魔』
上中下巻の内上巻を読み終えた。単行本の時はたしか上下巻だったと思うけど。全3巻は読み応えありそうだ。忍者物は大好きだし特に「風魔」という名には子供の頃から惹かれていたから読んでいて楽しいよ。
4月******************************
宮本昌孝『風魔』中巻
風魔の小太郎が真田の猿飛唐沢玄蕃を赦すところに悲哀を感じる。関ヶ原の後、着々と徳川が体制を築きあげていく中、如何なる勢力にも属さず風魔衆は何処へ向かうのか。さあて最終巻へいくぞ。
宮本昌孝『風魔』
これこそエンタテイメント時代劇の傑作だ。物語は戦国の終わりから徳川草創期を舞台として、その時代背景と実在人物を巧みに取り込み、史実の裏で暗闘を繰り広げる忍者集団や武芸者達そして悪党をスリリングに交錯させる。そしてなにより主人公風魔の小太郎の素晴らしさ!「風魔の小太郎とは、この武士の世で、戦闘者として恐るべき能力を持ちながら、自由に生きたいと願い、実際にそうしているという、信じがたいほど希有な存在なのである。」しかしそんな孤高な存在に為政者側は怒りと不安そして恐怖を憶え、抹殺を試みる。とにかく戦闘場面が凄い。息つく暇のないくらい引き込まれる。戦いの物語なのだが、このラストはじつに良い。おかげで幸せな読後感を味わった。巧い!お見事!
歌野晶午『黄桜の季節に君を想うということ』
読み始めたんだけど、どうもライト・ノベルに感じられて物足りない。その年のミステリーの賞を総なめとかあるけど、あの時本作の単行本に食指が動かなかったカンのようなものは正しかったと文庫本を読み終えてみてわかった。俺はこのテのミステリーが好きじゃないんだよね。登場人物をボカシて時間軸をずらして、じつはこうだったんです、というような話しがね。登場人物が魅力的じゃないとつまらないし、これはストーリーもイマイチで、どうしてこれがミステリー・ファンにうけたのかワカランな。
平岩弓枝『黒い扇』上下巻
昭和
30年代のミステリー。ストーリーも登場人物も物語の背景も申し分なし。平岩さんは『御宿かわせみ』など江戸市井物にも、さらりとミステリーを織り交ぜて、素敵な腕の冴えを見せる作家なので、この昭和の30年代に書かれた現代ミステリーも面白いに違いないと読み始めたのだが、大正解!刑事や探偵が出てこないミステリーとしても新鮮だった。そういえば近頃のTVドラマ、安直な刑事モノが増えすぎだよね。
金井美恵子『柔らかい土をふんで、』
ページを開くと見開きびっしり四角く文字の塊、それが最初から最後のページまで続く。会話カッコも改行もほとんどない。苦手なブンガク、とたじろぐ。最初は慎重に言葉を踏みしめながらページをめくったけど、しだいに言葉のアシの草むらをかき分けながら、とにかく先に進もうと頑張った。どこかでナニかが見つかると...。厚い小説ではないし、けっこうオシャレな雰囲気は感じる。でもナニかが見えては消えてゆく。引用とイメージのコラージュって感じで映像が浮かぶのに、次々とはぐらかされる。金井さん曰く「貧しい文学の世界を豊かにする」小説、賢い婦女子や青年達に読まれて欲しい。いやはや文学修行の足り無さを痛感(笑)
5月*****************************
冲方丁『天地明察』
素晴らしく爽快な小説。江戸時代、貞享の改暦の中心人物渋川春海を主人公にした物語。困難な学問に呻吟し、行く度もの挫折を味わいながらも、そして四十の歳を越えても、主人公渋川春海には青春の輝きがあった。困難に立ち向かう颯爽とした姿が物語りの最後まで続き、また春海を取り巻く学者達の熱い探求心もあり、まさに青春小説としての眩しさに満ちていた。鎖国の江戸時代に、算学や天文学といった分野の優れた学究の徒が切磋琢磨したことが、学問を鎖国状態から救い、明治の急速な近代化を可能にしたのだと思えてくる。
北方謙三『楊令伝
十三』
遼王より護国の剣を与えられた将軍簫珪材、宋禁軍総師童貫の秘蔵っ子で童貫亡き後は地方軍閥を率いる岳飛、この両雄の対決が素晴らしい!楊令伝全編中屈指の名シーンとなること間違いなしだ。悲運の名将とはまさにこの二人のことだね。
豊島ミホ『リテイク・シックスティーン』
いきなり「ねえ、誰にも言わないでね、誰にも言わないでね」.....「あたし、未来から来たの」と告白される主人公沙織16歳高校1年生。未来から来たという孝子は、2009年27歳から16歳に戻ってきたという....。この小説、このキテレツな設定を除けば、まあフツーの素敵な青春小説なんだよね。この未来から来た設定を、SF的にもましてやホラーやオカルト的に扱わないのが本書のキモ。未来から戻ってきたと孝子から唯一告白された沙織の戸惑いが、この青春小説の底流に流れる。まったく(笑)小説家ってのはいろいろやるよね。たいへん面白かった。
浅田次郎『月島慕情』
大正時代の吉原を舞台にした表題作に先ず涙。吉原の太夫が「アイ・ラブ・ユー..」「ばかやろう!」とハイヒールを月島の月に向かって投げつける...。泣けるねえ。「めぐりあい」は雪国の温泉でマッサージ師として暮らしている女性の悲恋話し。「シューシャインボーイ」は立身出世の裏話に泣ける。まったく浅田次郎は泣かせ上手だ。
北重人『鳥かごの詩』
サキちゃんが愛おしいなあ。哀しくなるくらい愛おしい。昭和41年、東京下町の新聞販売店、主人公康夫は住み込みの新聞配達員をしながら予備校に通う浪人生。その新聞販売店で出会った様々な人々と、ささやかで切実ないくつかのできごと。中でも康夫と博徒な爺さん一族との関わりが、この物語にコクと潤いを与えている。そして博徒な爺さんの孫のサキちゃん。彼女なくしてこの物語はない。マドンナのいない青春物語なんかつまらないからね。今では懐かしい昭和の人達が生き生きと描かれた、これは作者の自伝小説でもあります。とにかく北重人の全作品を読むのが今年の目標であり楽しみです。
北重人『夏の椿』
『蒼火』に続く立原周乃介ものですね。風景描写がじつに巧い。海に面した江戸の町、掘り割りの様子に行き交う小舟。読んでるうちに江戸の町が鮮やかに甦り、そこで暮らす人々の生活が見えてくるような、そんな描写力の確かさを感じるんだよね。その上、剣戟描写の迫力がもの凄い。やはり北重人は凄い作家だった。
6月******************************
北重人『月芝居』
これも面白かった!相変わらず風景描写が冴えている。北さんは建築家として都市環境計画の仕事をしていたとある。だからなのか、文章から江戸の町が鮮やかに立体的に立ち上がってくる。また人物描写の巧みさ、とくに本作の悪人はその賢さと剣の強さで際立つ。まあ北さんの小説に登場する悪人はみんな強敵なんだよね。相手が強いからハラハラ気が抜けない、だからなお面白いってことなんだ。
北重人『汐のなごり』
巧い!風景描写から心理描写が透けて見える。風景を望むその人の心の有り様が伝わる。本作は江戸時代、出羽の湊町水潟を舞台とした短編集。北自身の故郷山形県酒田市を思わせる北の湊の物語。得意の剣戟描写はないが、市井ものとして、その人物造形に細やかな情感、とにかく巧い。
宮部みゆき『小暮写眞館』
読む時間がなかなか取れず、しかも厚かった。これは宮部みゆきの軽さの新境地かな?(ライト・ノベル風)というような小説。高校生の兄と小学生の弟を中心とした家族小説&青春小説、それに心霊写真やら幽霊やらカルト・ムービーやら鉄道マニアやらが絡む絡む(笑)。たいへん面白かったけど、俺の望む宮部みゆきとはちょっと違うなあ。カバーの写真には星みっつです!
関川夏央『「坂の上の雲」と日本人』
「司馬遼太郎は(明治の始めから)日露戦争までの日本を、若い健康な日本と考えました。若くて健康な日本の受難とその克服を、『坂の上の雲』にえがききったわけです。しかし、その健康であったはずの明治の40年がその後、昭和20年に至る不健康な40年をなぜ生んだのかと考え続けたのでありました。....」という真摯な考察にみちた本書は、現在の私達日本人を鋭く照射して眩しいのだ。
速水健朗ほか『バンド臨終図鑑』
1961年から現在までの洋の東西を問わずジャンルも問わずの200バンドの解散模様を足早の語る本だった。「ハナ肇とクレイジーキャッツ」から「羞恥心」まで、臨終図鑑と言えども基調は軽いんだなあ。そんな中でルースターズの章は感動的だった。リーダーの大江は重度の健康面と精神面の不調を抱え続け、バンドから(入院などで)離れていたていた。そんな時、大江以外のメンバーはロックンロール・ジプシーズとして活動を開始、結成の理由は「大江君を励ましたかったから」だった。そしてルースターズとしてのフジロック出演の話しが湧き上がる。これをバンドのラスト・ライブにしようという働きかけ。この話しに大江も花田も泣いた。....ロックンロールの気骨を感じさせる良い話しだった。
7月***********************************
船戸与一『新・雨月 戊申戦役朧夜話』上下
船戸与一は民衆側に立って骨太な活劇物語を書いてきた作家だ。だから船戸にとって、支配階級である武士とその支配下で生きる民衆を対峙させるのが彼本来の作風だと思っていた。本作でも河井継之助及び長岡藩士や会津藩士が戊辰戦争において、農民を初めとする領民のことを思い諮ったとは思えない。彼等武士にとっては藩と藩主こそが大事で、領民は当たり前にそこに暮らし働き年貢を納める下層階級の人達なのだ。戦となれば田畑を荒らし村を焼き、村人を徴用し女性に乱暴する。これは当たり前に戊辰戦争でも行われたことなのだ。本作でもそのような場面は多く出てくる、でもなんだか物語の歯切れが悪く、登場人物の造形も船戸にしてはイマイチだ。何故だろうと読み進む。船戸は戊辰戦争を調べ書き進めるうちに、武士の滅びる姿に美しいものを感じてしまったのではないか?武士道とは手前勝手ではあるが美しくもあると感じたのではないか。民衆からみたら悪そのものの武士の戦、なれど武士にも...そんな思いが、この物語の詰めを甘くしたように感じた。
樋口毅宏『日本のセックス』
たしかに淫乱三昧な小説ではある、本の中程までは。そこからどんどん転落する。物語が陰湿にならないのはヒロインが自分の悲惨な状況をどこか醒めた第三者の眼で見ているからか。面白い小説だったけど、読み終えた時は妙に醒めていた。
樋口毅宏『さらば雑司ヶ谷』
樋口作品を続けて読んでみた。こちらは乾いたバイオレンスだね。暴力小説。ドライな暴力描写は花村萬月を思わせるけど、それより『鉄コン筋クリート』みたいなマンガに近い乾きぐあいだ。主人公のバックに婆さんが統べる闇の組織があるって構造は『男一匹ガキ大将』のようで、こうゆうバックボーンはズルイと思う。これでハードボイルドとしては失格だ。『日本のセックス』も『さらば雑司ヶ谷』も、主人公が人間不信なとこが共通かな。『日本のセックス』の中に「十人十色というけど、ほんとは一人十色なんだよ」みたいなセリフが出てくる。一人十色と人間不信が結びつき暴走するニッポン物語なのか?。
宮原芽映『海の見える観覧車』
宮原さんとはツイッター繋がりで、お互いにフォローしあっている。彼女は'78年頃タイニー・パンプスとして歌手デビュー、その後は作詞家としても活躍、作詞のリストには渡辺はま子からレベッカそしてアニソンなどとじつに幅広い。そんな宮原さんが暮らしている横浜の街をエッセーとして書き綴ったものが本書『海の見える観覧車』。鶴見線海芝浦駅に向かう古いチョコレート色の電車のはなしが特に印象に残った。
レジナルド・ヒル『骨と沈黙』
この厚さに見合う圧巻な英国ミステリいや「偉大な英国小説」。警視ダルジールの人間的ブ厚さが凄いね。この威厳に満ちた強烈なユーモアと毒はイギリスならではと思う。これはちょっと快感。物語の主軸はミステリなんだけど、サッカーのフーリガン、失業問題、文学論、神学論争を絡めて、たんにミステリに留まらない内容豊かな小説となっているとこが「偉大な英国小説」たる所以か。もちろんミステリとして超一級ですよ。
浦沢直樹『BILLY BAT
4』
面白い!「テキサス捕物帖ピストルヘアー荒野を行く」なんて笑っちゃうくらい素敵だ。まるでパラレルワールドのように多くの物語が複雑に絡み合って進行しているようで、前巻ではそれが少しとっちらかってる印象があったけど、ここではグッと締まった感じで、さらに引き込まれてしまった。いったいこのストーリーは何処へ向かって行くのか、楽しみなような怖いような(笑)。
8月********************************
坂東真砂子『ブギウギ』
坂東さんによる真っ当なミステリー小説。やはり巧い。終戦を挟んだあの頃、箱根に抑留されていたドイツUボート乗組員達に纏わるミステリー。この舞台設定が効いている。その舞台以上に物語りのスケールが大きいのは、時代背景を巧く取り入れているから。面白かった。
マイケル・バー=ゾウハー『ベルリン・コンスピラシー』
久しぶりの謀略エンタメ小説、じつに面白かった。『エニグマ...』『パンドラ...』を読んだのはずいぶん前(30年前?)なので、ゾウハーのサスペンス・タッチがどんなだったかは思い出せなかったが、とにかくスパイ物の大家である。本作も英国MI6、米国CIAがしっかり悪巧み、でもソ連KGBが登場しないところが30年前との違いですね。それでも英米スパイ小説最大の敵としてKGBと並ぶナチスはしっかり登場。恐ろしい幻影として。ドイツを舞台にユダヤ人を軸に、ネオナチ台頭への恐れを背景に、個人の正義と大国の不正義がスリリングに絡み合う。ラストのラストがなんともいえない余韻となった。
北方謙三『楊令伝
十四』
梁山泊軍と南宋軍の全面対決。物語はクライマックスに近づきつつあるのかな。帝のいない国、自由市場による民が富める国を標榜する楊令の志がようやく見えてきた感じがする。戦場を駆けまわるのは若き将軍達、花麒麟、呼延凌、秦容。みな梁山泊二世だ。そんな中、英傑九紋竜史進がひた走る。その先には、、、。俺が気を持たせてどうする(笑)。久しぶりの大合戦シーン、そのスペクタクルに酔う。
山本兼一『命もいらず名もいらず』
「幕末の三舟」として勝海舟、高橋泥舟と共に並び称される山岡鉄舟の物語。幕臣であり、書の達人であること、それ以外のことは知らなかった鉄舟のこと、読んでみてビックリ仰天のまさに巨人であったことがわかった。高位の侍従として明治天皇に仕え、その毎日の勤めを終え帰宅すると、先ず弟子たちと剣道に励み、夕食に晩酌。晩酌は二日酔いにならない程度に毎晩二升から三升(!)。それから筆を持ち書を数百枚書き、そして真夜中まで坐禅。公案の答えを考えるに、脳みそに汗をかく程、坐禅をくみ考えた。これが鉄舟の日課だったそうだ。剣も書も禅も一流の人であったが、終生お金には無頓着で貧乏は平気だった。『精神満腹』とはいい言葉だ。
小川洋子『夜明けの縁をさ迷う人々』
去年の傑作『猫を抱いて象と泳ぐ』を想わせる短編集だった。解説で村田喜代子さんが指摘している「この短編集の作品群を成り立たせているものは、奇妙な時間の連続性であるとしか言いようがない。...メリーゴーランドのように回り続ける世界。いつまでも終わらない連続運動のような永劫回帰的な世界だ。」と。哀しさには様々な感情があるのだということを考えた。そういえば「涙は悲しさだけで、出来てるんじゃない」って歌がムーンライダーズにあったな(笑)
萩原朔美『劇的な人生こそ真実〜私が逢った昭和の異才たち』
登場する異才は、『家畜人ヤプー』の沼正三、パルコを作った増田通二、暗黒舞踏派土方巽、森鴎外の長女で小説家森茉莉、御存知寺山修司、萩原朔太郎の娘で小説家で著者の母萩原葉子、美術評論家東野芳明、以上の面々。みんな一風変わった魅力的な人達だ。中で目からウロコだったのが東野の文化芸術に対する持論で「...文化の主体は、作り手ではなく、受け手なのだ。新しい美術が
" わからない "
と決めつけられるのも、それを自分の時代のなまなましい表現としてうけとめる、観衆の厚みがないからだ。美術大学にしても、作り手中心ではなく、そんなドン欲な受け手を発生させる場に、と発想を転換する時に来ていると思う。芸術家なんぞという異分子は、放っておいてもなるものはなるのである。...」ということ。なるほどと肯ける考えだよね。萩原朔美というひとは、名前はずっと前から知っていたけど、天井桟敷の役者で演出家だったとか、だけどその名前のわりにはワカラナイひとだった。読んでいて思い出したのは、あの「ビックリハウス」を創刊した人なんだよね。"
放っておいてもなるものはなる "
そんな人なんだな、萩原朔美って。
横溝正史『人面瘡』
数ヶ月前から一編一編箸休めに読んでいた短編集。5編のうち3編がお馴染み岡山県警の磯川警部モノ。つまり、離島や山奥の旧家絡みの殺人事件。まあいつもどおりの展開。東京を舞台とした金田一モノが好きな俺として「眠れる花嫁」が良かった。昭和20年代東京の、いかにも怪しげな人達が蠢く様が、闇の濃さと相まって、独特な風情を醸し出していて、ちょっとゾクゾクとするんだよね。横溝正史は、ミステリーとして楽しんだことはなくて、こんな日本もあったという風俗小説として面白く読んでいる。
絲山秋子『絲的メイソウ』
ずいぶんと赤裸々なエッセイ集だった。俺より10歳若い女性で作家の、日々噴飯モノ日記だった。気分が落ち込み憂鬱な時のテーマ・ソングがジェームス・チャンスだってのが気に入ったよ。
9月***********************************
長嶋有『夕子ちゃんの近道』
長嶋有の父親は『古道具ニコニコ堂です』なんて本も書いている古道具店の店主だそうだ。本作の舞台は「フラココ屋」という西洋アンティークほかよろず取扱いのまあ古道具屋のようなお店。馴染みのある環境を舞台にしているせいか、自然な感じで風通しのいい連作短編集だった。ただこの風通しの良さは、登場人物一人一人の軽さが一因かとも思う。主人公の名は明かされない。周りの人達にも細かい人物造形は感じられない。これは主人公とその周りの人達という群像を、その空気感を察知して感じて読んでくれという作品かなと思ったりもした。この感じは好きです。
ジョン・リーランド『HIP:THE
HISTORY/ヒップ - アメリカにおけるかっこよさの系譜学』
「...第二次世界大戦後にあたるヒップの第三の結節点には、恩寵と至福を求めてメインストリームを拒絶したふたつの知的運動、ビバップとビート・ジェネレーションが並行して誕生した。これこそがヒップの黄金時代であり、のちに続くカウンターカルチャーにとってのテンプレートとなった。」!!!おおっかっこいい!と大きく肯く。『HIP:THE
HISTORY/ヒップ -
アメリカにおけるかっこよさの系譜学』(ジョン・リーランド著)を読んでいるのだ。 「すべてのアメリカ近代文学は、マーク・トウェインが書いた一冊の本、『ハックルベリー・フィンの冒険』から始まる」とヘミングウェイが述べたことは知っていた。が、「『ハックルベリー・フィンの冒険』は、方言、エスニックな人物造形、喜劇的な誤解などを完備した、いかだに乗ったミンストレル・ショーだといえるだろう」はジョン・リーランド著『HIP:THE
HISTORY』のいかした記述。ブ厚い本だけど、かっこいい(HIPな)言い回し満載で刺激的かつ楽しい本だ。
山田風太郎『甲賀忍法帖』
理屈抜きに面白い。まあ面白いことはわかっていたけど、流石山田風太郎大先生です。伊賀・甲賀忍者の精鋭が10人ずつがトーナメント的な感じで命をかけて戦う。その奇抜な忍法たるや...忍者に夢中だった少年時代を想い出した。この作品は昭和33年連載開始とある。思えば、昭和の30年代って忍者の一大ブームだったんじゃないかな。マンガにテレビに小説にと忍者は大活躍。またマンガ雑誌の広告に手裏剣などの忍者道具が載っていたのもこの頃、つまり俺の少年時代だった。『甲賀忍法帖』を読みながら、そっくり似たマンガを想い出した。横山光輝の『伊賀の影丸』だ。『伊賀の影丸』も忍者集団による十番勝負が面白く強く印象に残っている。忍者モノってのは、俺達世代男子の一大ロマンだったような気がするなあ。
北重人『夜明けの橋』
タイトルがいいね。作者が得意とする江戸幕府草創期の物語。短編集で、それぞれに時代の夜明けを感じさせる。戦国の世が終わり、武士も生きる道を模索する。戦国武将モノのような有名な武士のかっこうつけた話ではなく、主が敗れ名もなく禄もない武士の懸命に生きる姿が清々しくもあり、また武士の世の終わりを寂しく思う気持ちも背景としてあり、時代の節目をさりげなく捉えた冴えた視点の物語だと思う。北重人は全部読もうとここまで来て、残るのはあと1冊となった。もったいなくてすぐには読めないなあ。
小西康陽『マーシャル・マクルーハン広告代理店。ディスクガイド200枚』
パラパラ読み続けている。裏表紙には彼のスタンス表明がある。曰く「CDなどまったく集める価値がない。まして音楽配信など以ての外。1974年以降の音楽に聴くべき価値などない。同じく1974年以降に生まれた女性にも興味を失った。この世にはダンスのための音楽と独りで聴くための音楽しか存在しない。そもそもディスクガイド本を買う人間に音楽がわかるはずがない。」と怪気炎!(笑)まあその割り切り方は良し、としよう。本書はディスクガイドとしてより、音盤にまつわる二三の事柄をロマンティックに書いた本として面白い。また知らない音盤がたくさん登場して刺激的だ。
10月・11月・12月*******************************
平安寿子『おじさんとおばさん』
身につまされる、おじさんおばさん小説だった。そこは平さんだからユーモアいっぱいなんだけど、でも身につまされた。俺も五十代だからね。登場人物は小学校の同級生で五十代後半の男女6人。様々な障害を抱えながらも皆さん男女でトキメキあうのだ。これは五十代のトキメキ小説だな。でも渡辺淳一じゃないから、登場する皆さんはごく普通の五十代、うっとりロマンティックなんてことはない。現実はキビシイのだ。そして皆さんは大人なのだ。ラストの『希望』(あの大ヒット曲の)が巧いオチとして歌われる、この落とし方は見事です。
T・R・スミス『チャイルド44』上下巻
読み進むのが辛くなるような部分もあったけど、終わってみるとその展開の巧さに舌を巻く。ソ連もの、警察監視国家の恐怖、「この国には犯罪は存在しない、理想の国ソ連」という建前、スターリン時代のソ連を背景(この背景が主役かな)に、元エリート捜査官とその妻が国家から犯罪者(反革命分子)として追われながら、連続殺人事件の犯人を追い詰める。登場人物のその端役にいたるまで丁寧な人物造形がなされ、その臨場感が胸に迫る。ミステリイ・スリラー・ホラー・スパイ・冒険小説として見事な一作だった。
高田郁『花散らしの雨〜みをつくし料理帖』
シリーズ1作目の『八朔の雪』がとても胸に沁みたので、2作目も読んでみました。そしてまたじ〜んときましたねえ。「...その刹那。障子の隙間から、そっと白い腕が差し出された。夜目にも真っ白な細い女の左腕。その手の先が狐の形に結ばれる。...
涙は来ん、来ん 」幼なじみの野江ちゃんは吉原の花魁、顔を見せない代わりに、幼い頃ふたりでよくやったサインの交換をするシーンです。涙は来ん、来んは狐のコンコンにかけてあるんですね。このシリーズは料理帖とあるように、主人公澪による季節の素材を生かした料理が作中で振る舞われ、それはまた読んでいる読者にも振る舞われているのです。美味しいですよ、想像の御馳走。
奥田英朗『家日和』
夫婦と住処に纏わる六つの短編。別居、倒産、ネットオークション、ロハス、恋心、、、家庭に訪れる大波小波を名手奥田がささっと捌き読後感良し。中でも「家においでよ」。主人公は別居で一人暮らしになったのを機に、押し入れにしまってあった『レコードコレクターズ』のバックナンバー10年分を本棚に並べるんだよね。親近感が一気に湧いたよ(笑)。「妻と玄米御飯」では、妻がロハスに目覚め、夫と息子達は「たまには豚カツが食べたい」と抗議する、ってのも可笑しかった。
近藤ようこ『逢魔が橋』
近藤ようこも漫画王国新潟の出身です。だからって贔屓にしてるわけでもなく、そんなこと知らなかった『仮想恋愛』(青林堂)の頃から好きな漫画家です。『逢魔が橋』は最新作で舞台は中世日本。「...その橋は 静かな山中に 人知れずあった...」と始まります。橋のたもとには橋守がいます。この橋守は、橋を渡ろうとする人々の心の底が見えてしまう人ならぬ者、、、。今や、このヒンヤリと澄んだ物語世界は貴重なものです。近藤ようこの漫画は漫画ならぬ漫画だったりするね。
向田邦子『男どき女どき』
妻の本棚からしっけい。短編小説にエッセイが加えられている。テレビ・ドラマの人気脚本家としてしか知らず、それも「寺内貫太郎一家」のような見ていて面白いものしか知らなかったので、初めて向田邦子の小説を読んだ時(「思い出トランプ」だったか..)、そのいじわるな視線に驚いた。いじわるはひどいね。人の内面をあばき出す視線かな。そしてその視線の拗ねている感じが可愛いく、ああ向田さんて素敵な人だなと思ってしまう。ホーム・ドラマにヒヤリを持ち込む手腕は、この人の真骨頂だった気がする。
大沢在昌『ブラックチェンバー』
警察、公安、暴力団、ロシアン・マフィア、そして正義を標榜する謎の組織ブラックチェンバー。大沢らしい小説だ。ハードボイルドを読み始めた20代の頃からずっと大沢の小説は好きだった。だが、どうもいけない。悪辣な連中が騙し合い殺し合う小説が、もう楽しめなくなった。暴力や殺人を含む活劇が嫌いになったわけじゃない。どうも大沢ハードボイルドのストーリー仕立てがエンタテイメントとして楽しめなくなった。元北朝鮮の女性工作員チヒの活かし方にも疑問が残った。まあ読むこちらの体力が低下しているってことかもしれないけど(笑)
北重人『火の闇〜飴売り三左事件帖』
これで北の既刊は全て読んだわけだ。そしてここに収録の「火の闇」が彼の絶筆だった。北は去年の8月、61才であの世へ旅立ってしまった。2004年『夏の椿』でデビューだから遅咲きの作家であった。しかし残された作品はどれも艶やかに磨き込まれた文章による素晴らしいものばかりだ。彼は1級建築士であり、都市計画の専門家でもあった。それゆえか、彼の描く江戸の街並みや水路の様子には立体感と臨場感があった。風景の描写も人物の造形も素晴らしかった。そのうえ、忍者ものや剣劇といった活劇シーンもじつに巧かった。つまり、デビュー時にはすでに出来上がっていた成熟した作家だった。全作品を読み終えた今、あらためて冥福をお祈りする。
山田風太郎『太陽黒点』
山田風太郎の現代小説は初めて読んだかな。忍者モノや明治開化モノは読んでいたし、それで風太郎ファンになったんだけどね。『太陽黒点』は1963年の書き下ろしで、第一級のミステリ長編とあります。ミステリにはミステリだけど、、、なんかね、暗い悪意が底に流れる青春小説って感じかな。戦争で悲惨な青春を送らざる得なかった者が、戦後の明るい太陽族に象徴されるような若者達に向ける陰湿な視線。そして60年代にはまだ一般的に存在した階級意識。そんなものを底流とした小説だから暗く陰惨で、風太郎がこうした小説を書いていたことがちょっと以外だった。たしか劇画や映画でも、こんな感じのストーリーはあったよね。でもこの小説が特異なのは、その犯罪がシミュレーションが目的で、その結果は失敗なら失敗でもよかった、ということ。ミステリというよりは犯罪シミュレーション小説という感じを強く持った。
明野照葉『家族トランプ』
主人公窓子は30代独身、中野区の自宅から通勤の会社員。父母との気まずい三人暮らし。ひょんなことから先輩キャリアウーマン潮美と友達関係になり、彼女の三ノ輪の実家で素晴らしい家族と出会う。まあそんなお話し。三ノ輪の人達は皆心温かく主人公を癒してくれるという、ちょっと出来過ぎな感もあるけど、まあそこは物語だから、、、読後感良しってことで。
北方謙三『楊令伝 十五巻』
あ〜〜終わってしまった。寂しいよ〜。2006年に『水滸伝』(全十九巻)を読み始めて、その続編だった『楊令伝』(全十五巻)。素晴らしい英雄譚だった。女っ気のまるでない(すこしはあった)物語だったのに、そんなこと忘れていたくらいに凄い漢(おとこ)達のオンパレードだった。宋江、晁蓋、呉用、公孫勝、盧俊義、燕青、阮三兄弟、呼延灼、豹子頭林冲、九紋竜史進、青面獣楊志、穆弘、秦明、花栄、戴宗、王進、魯智深、武松、李逵、花飛麟、呼延凌、秦容、そして楊令。敵役に童貫、李富、そして岳飛。蕭珪材も忘れられないな。スリルと臨場感たっぷり、大スペクタクルな合戦シーン。頭領として孤独に向き合う宋江そして楊令。野放図で豪快な李逵のなぜか肉料理。まだまだある...とにかく感想として何を書いて良いか困るほど面白すぎる物語だった(と過去形に泣く)。ただただ北方謙三に感謝するのだ。
花村萬月『ウエストサイドソウル』
なんかコバルト文庫だったなって感想。花村ファンとして、そしてあの傑作ブルース小説『ブルース』を書いた萬月のブルース小説だってのでもの凄く期待したのに、期待のしすぎで肩透かしって感じ。面白かったんだけど、俺の期待が大きすぎた、、、。主人公の少年が天才過ぎで、仲間が金持ち過ぎ、ようするに出来過ぎた話で、最後には読みながらシラケてきた。少年のあっけらかんとした理屈っぽさも、しだいに鼻についてきたし。あ〜〜〜残念。
日暮泰文『のめりこみ音楽起業』
俺をブルース・R&Bなど黒人音楽に深く引き込んだ3人、それは中村とうようと鈴木啓志と日暮泰文。'73年頃から読み始めた「ニューミュージックマガジン」で彼等が紹介したブルース・R&Bに興味かき立てられ、日暮が創刊した「ザ・ブルース」で更にずぶずぶ底なし沼に引き込まれるようにブルースを聴くようになった。日暮は更に雑誌だけでなく、ブルースをリリースするためのマイナー・レーベルを'76年に起こす。それが今も健在なP
ヴァインだ。Pヴァインはブルースに固執することなく黒人音楽中心にファンク〜ヒップホップさらにワールド・ミュージックなどにも枝を広げ、出版関係もブルース・R&Bに限らず様々な本・雑誌を刊行している。つまるところ、ブルース・R&Bだけに拘らなかったのが会社に幸いしたということだ。それでも「ブルース&ソウル・レコーズ」のような、その手のファンを喜ばす雑誌も出しているから、変節したわけじゃないんだよね。そんな会社のオーナー社長として頑張った日暮泰文さんの起業記だから大変に面白かった。本の帯のコピーが「非メインストリームに生きよ」。このコピーに乗せられて買ったようなものだけど(笑)ありがとう!日暮さんとPヴァイン。感謝しています。
志水辰夫『引かれ者でござい』
'81年のデビュー作『飢えて狼』から、そのほとんどの作品を読んでいる大好きな作家志水辰夫だが、本作の前編とも言える『つばくろ越え』を読んでいなかったことを悔やむ。こんなに面白いシリーズを読み忘れていたなんて。本作は幕末の飛脚の物語。「通し飛脚」という列島を単独で横断する飛脚のお話だ。舞台は本街道から外れた山奥。そんな山奥にも人々の営みがある。飛脚が山中を駆ける様には、冒険小説の趣もあり、村人との交情には深い人間ドラマがある。三編の短編から成っていて、短編ならではの話の落とし方もじつに巧い。流石は志水辰夫だ。
角田光代『ひそやかな花園』
小さかった頃、親と一緒に参加した " 夏のキャンプ "
。高原の山荘に、普段付き合いのない数組の家族が集まり数日を過ごし、そして数年間だけ続けられたそのキャンプ。大人になった
" キャンプ "
の子供達が、お互いの所在を探しあい、あのキャンプの謎に迫る。ちょっとミステリ風な面白さに惹かれながら、こわい真実に向けて謎が解かれて行く後半は、重いテーマを読者も委ねられたような感じになる。角田光代は再生の物語が巧い。
池上永一『トロイメライ』
「お前が憎いっ!お前が憎いっ!お前が憎いっ!」「アガーッ!アガーッ!アガーッ!お許しください長老様。」この大貫長老と新米筑佐事(岡っ引き)武太の、毎回出てくるやりとりが可笑しい。時は幕末琉球王朝時代、舞台は那覇。江戸市井物語を那覇に置き換えた趣もある。主人公は岡っ引きの武太。仕事はまだまだ半人前だが、三線と唄は天才的(本人の自覚は薄い)。事件のない夜は長虹堤の畔で三線を弾く。「民は唄の巧い武太を平和の声と親しんでいた。長虹堤で唄が聞こえる夜は、王国が平和だったという証拠だ。」と作中にあるとおり。武太の唄い奏でる琉球の歌と共に、物語りの重要な役割を果たしているのが、鍋(ナビー)・竈(カマドウ)・甕(カミー)という名前の三姉妹が料理の腕をふるう「おなり宿」。三姉妹が作る琉球料理がじつに美味そうで、読みながら腹が鳴る(笑)。民謡と料理に彩られた那覇の民の物語りに、そこにまた実に魅力的な人々が絡む。謎の覆面義賊
" 黒マンサージ "
、絶世の美女ジュリ(遊女)の魔加那、そして民の救済所涅槃院住職大貫長老など、キャラ立ちがじつにお見事!
あ〜面白かった。続編を是非お願いしたい!それにしても池上永一、近未来小説『シャングリ・ラ』の重厚さも良かったけど、この琉球物の方が俺は感心した。ということで、今更ではあるが『テンペスト』も読むことにした。
中森明夫『アナーキー・イン・ザ・JP』
にわかパンク少年がイタコおばばにシド・ヴィシャスの降霊を頼んだら、降りた霊はなんとアナーキスト大杉栄だったというお話し。しかも大杉がパンク少年の脳内に巣くってしまったからさあ大変面白い。大杉栄の大きさが現代を軽く飲み込み、パンクを軽く飛び越えカオスに至るアナーキー青春小説だ。戦前の左翼〜無政府主義者が次々に登場し、それは日本だけじゃなくてロシアやパリへも広がるという脳内タイムマシン小説でもある。おまけに可愛いアイドルともイイコトやっちゃって、、、(笑)
いやはや面白かった。
▲
|